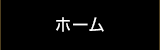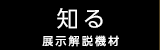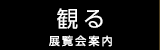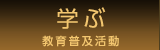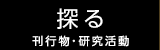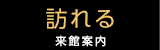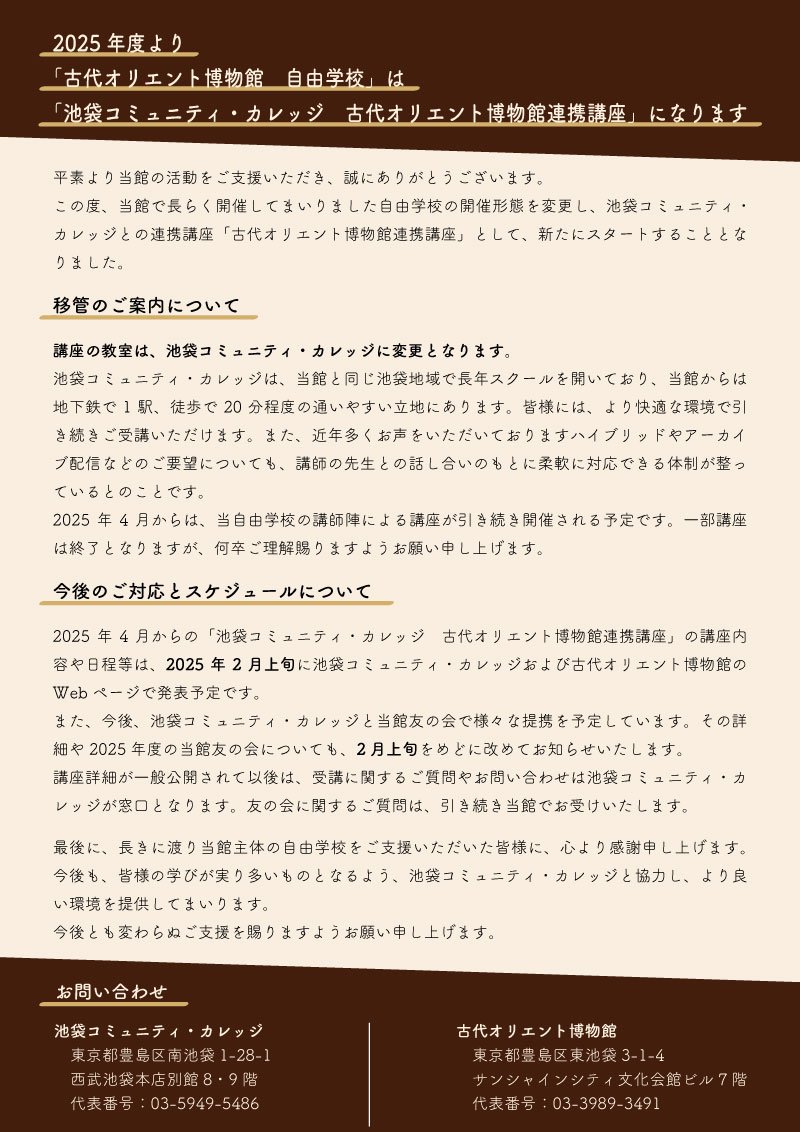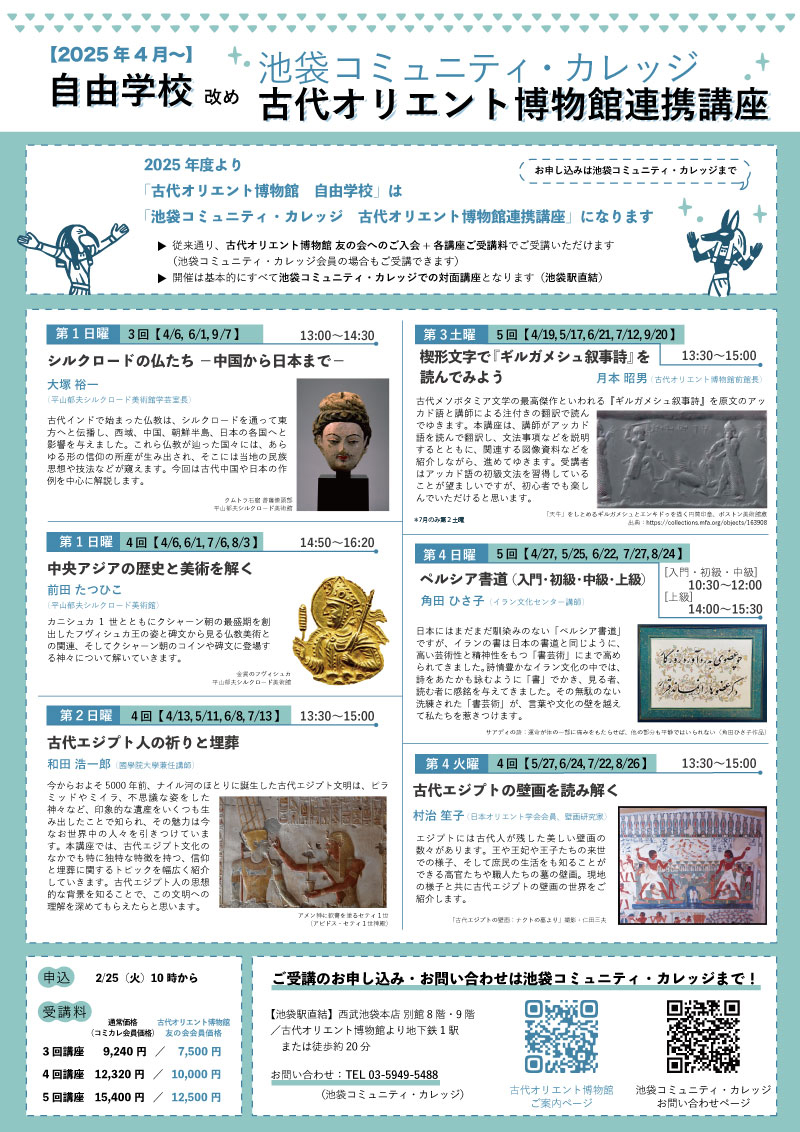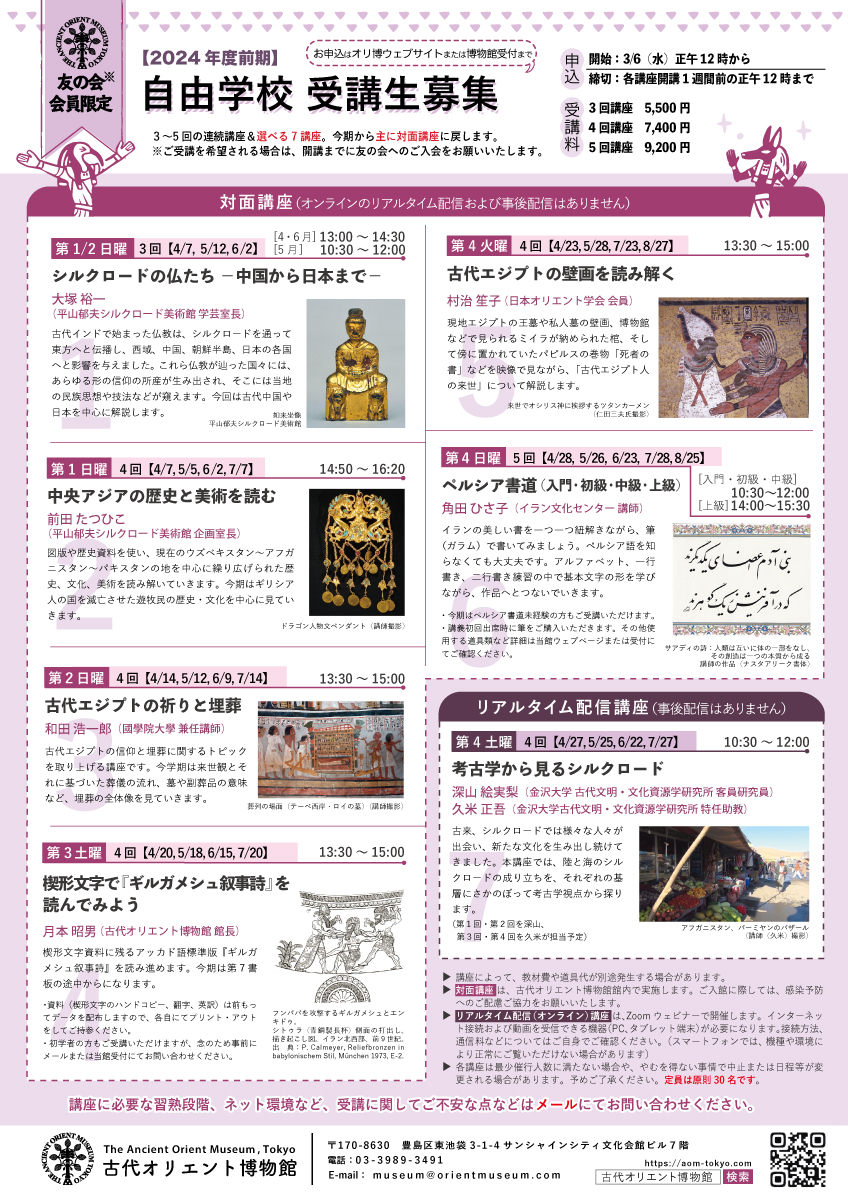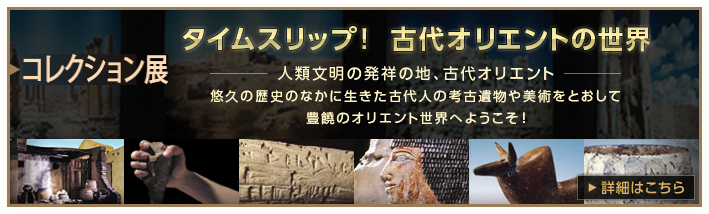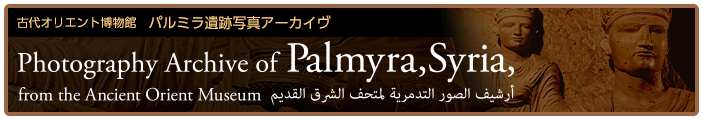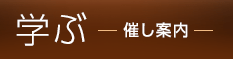自由学校(改「池袋コミュニティ・カレッジ連携講座」)

目次
→ 2025年度 自由学校に関するお知らせ
…… お申し込みの流れ(2025/2/19公開)
…… 2025年4月期 開講講座の詳細(2025/2/19公開)
→ 2024年度自由学校(終了)
2025年度 自由学校に関するお知らせ
重要なお知らせ:
2025年度より、「古代オリエント博物館 自由学校」は「池袋コミュニティ・カレッジ 古代オリエント博物館連携講座」になります。
詳細については以下の通りとなります(下の画像をクリックすると大きくなります)。
池袋コミュニティ・カレッジ 連携体制につきまして
古代オリエント博物館と池袋コミュニティ・カレッジの連携体制につきましては、専用ページをご確認ください。
→ 「池袋コミュニティ・カレッジ」との連携について
お申し込みの流れ
オリ博友の会会員として受講する場合……
● オリ博友の会へご入会ください: 「友の会」詳細についてはこちら
● 【会員番号】お受け取り後、下記のいずれかよりご予約ください
・ お問い合わせフォーム
:「お問い合わせの講座名」に、お申し込みご希望講座を入力
:「お問い合わせ内容」に、オリ博友の会会員番号を入力
:その他必要事項(お名前・住所・お電話番号等)を入力
上記のようにご入力のうえご送信ください。
・ または、お電話( 03-5949-5488 )でもご予約いただけます。
○ 池袋コミュニティ・カレッジ会員として受講する場合……以下の各講座の詳細ページより、お申し込みへ進んでください。
「連携講座」2025年4月期 開講講座の詳細
各講座の詳細については、以下リンク先のページでご確認ください。
- 「楔形文字で『ギルガメシュ叙事詩』を読んでみよう」 月本 昭男 先生
- 「シルクロードの仏たち―中国から日本まで―」 大塚 裕一 先生
- 「中央アジアの歴史と美術を解く」 前田 たつひこ 先生
- 「古代エジプトの祈りと埋葬」 和田 浩一郎 先生
- 「ペルシア書道」入門・初級・中級(午前) / 上級(午後) 角田 ひさ子 先生
- 「古代エジプトの壁画を読み解く」 村治 笙子 先生
※チラシ画像は2025年2月時点での内容です。講座内容・開講日・募集状況などの最新の情報は、必ず各講座のリンク先のページをご確認ください。